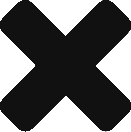殺し屋を乗せたタクシーの運転手が、その仕事にコラテラルされる話。
殺し屋にしては事前・事後の処理がものすごく雑だ。殺る前にロケーションを一切確認せず、殺った後もスナイパーならともかく死体を放置したままその場を立ち去るプロなんてありえない。挙げ句ストリートで絡んだチンピラを殺してしまい、それまでも放置して去るなんて馬鹿の極みだ。だがしかしこういうずさんな部分がなければマックスがこのセミプロ殺し屋に巻き込まれる状況もないだろうし、それこそ、本当に不動産屋の得意先回りに付き合って一晩比較的稼ぎの良いタクシー稼業を全うした気になっているだけの映画になってしまう。
だがこの映画にはそういうダメな部分よりも「がんばれマックス」的な感情の方が上回ってしまう。それは、ヴィンセントというイレギュラーな状況を持ち出すことでマックスの背景をかなりかっちりと描いているためだろう。普段ターゲットのバックボーンなんぞしったこっちゃないために平気で殺せるヴィンセントが、背後を知ってしまったマックスだけは奇妙な親近感を得ているというのもなんとなくわかる。←だとしたらこれも殺し屋的にはダメなやつなんだが。
ラスト、前フリとして「ロスの地下鉄で死んだ奴が○時間放置された」みたいなことを語ったのを受けてのああいう状況なので、マックスは地下鉄のドアが閉まる直前にヴィンセントを担ぎ出すのかなあなんて思ってたら、なんとそのまま放置していきやがった。オチとしてまとまりやすい安直な人間らしさよりも、ヴィンセントの孤独感を最後まで貫いた形になった。その分オチは尻切れで、せづねえ感じになっている。
ただヴィンセントは6年しか殺し屋稼業やってないんだよなあ。ここは結構重要だ。だとすればずさんな事前事後処理も(経験不足という意味で)ある程度理解できるし、この風貌からして確実に「6年前=殺し屋になる前」の背景が、見えにくいがヴィンセントにもあるということだ。
要するに対比だ。生きることがアホらしくそれ故自分の命も他人の命もたわいないものとするヴィンセントと、タクシーをやりながらいつかハイヤー会社の立ち上げを夢見て、正直12年もルーティーンをこなして生きながらえているマックス、このように考えると最後に描かれる孤独感も非常に後味良いものだ。
全体で見ると前述したダメ殺し屋の部分や、クライマックスあたりからのマックスの(一般善良市民にしては)超絶な頑張りっぷりなど、はっきり言ってストーリーの荒は多い。だがしかし、マックスとヴィンセントの関わり方(タクシーの中での会話など)・大都市を舞台にしたもの悲しい感覚を中心に見ると結構楽しめた映画だった。
月: 2005年6月
KillBill vol.2 ★★★★★
結婚式で親族を惨殺された嫁が復讐の旅に出る話。の続き。
vol.1は一言で言えば「日本のやくざ映画を撮ってみたいという衝動」の映画だった。して一応ストーリーとしてはその続きであるvol.2は、やや「カンフー映画撮ってみたい病」の兆しもあるが、基本的には復讐のため女が各地を移動し、復讐敵と闘っていくのが主軸となっている。その点例えばカンフー修行からの墓ぶち破りシーンは時間の往来というタランティーノらしさを出しながら伏線の張り方として非常に映画らしいつくりを取っていたり、5点を押す必殺技が最後の伏線になっていたり、vol.1はアクションや音楽へのこだわりを強く感じたが、vol.2ではそれよりもストーリーや見せ場を重視した作りになっている。
そのためvol.1でぼんやりとわかっていたような女と4人の殺し屋の関係、またそれぞれとそのボスであるビルとの関係などが明らかにされて、より登場人物の心理や置かれた立場を掘り下げたものとなっているのも、ストーリー性が重視された印象を受ける要因かもしれない。
見せ場に関してはvol.1であったような大立ち回りのチャンバラはなく、vol.1の冒頭でもあったような、緩急を急激に付ける1VS1の戦いになっていて、スピード感を重視した見せ方をしているので殺陣の間も冗長に感じることはない。それどころか、例えば眼帯女との決闘ではあの殺陣の間にアイデア溢れる攻撃が繰り返され圧倒されるし、もちろんユマサーマンも眼帯女の役者さんも格闘技のプロではないが、編集や画面効果ひとつであれほど緊迫感のあるものが出来るのは驚きだった。
また今回もガチンコ体当たり勝負のユマサーマンは凄くて、特に生き埋めにされて脱出するくだりの緊迫感というか、見てる側も息が詰まってしまうほどのリアルさはあの表情・演技あってのものだし、タランティーノが気に入っているのもわかる。
というわけで、1と2あわせて見てみると、前半1のガチャガチャ加減と後半2の重厚さ+タランティーノ流時間の分断とチャプター方式+ガチンコユマサーマンという組み合わせはよかったし、大変楽しめた映画だった。
ギャング・オブ・ニューヨーク ★★★★★
南北戦争少し前のアメリカはニューヨーク、父親をギャング団の頭目に殺されたその子供が大きくなって復讐する話・・・・という体のアメリカ史映画。
見る前は「プリ男がギャングモノ?あのベビーフェイスでか?」と、いわゆるアクションをメインとした”マフィア映画”を想像していたんだが、実際見てみるとこれが全く違った。
アメリカの歴史についてはざっくりとしか知らない(フランス革命頃に独立戦争があって、1800年代中頃に南北戦争があって、1900年代以降は色々外国とも絡んでくるからまあまあ知ってる)ため、この映画も同様にざっくりとしか楽しめなかったと思う。例えば当時アイルランド移民が経済不況からアメリカに殺到していたという事実は知らなかったし、ニューヨークの自治がどのようになされていたのか、また風習や慣習を含めた文化的背景(奴隷制度とかracismとかそういう事ではなくてもっと細部に到る、服装・流行・喰いもんなど)、こういう点も映画の中から見極めるだけで、自分の中では全く消化しきれていない。史実映画は細部を楽しめるかどうか=その歴史について多少なりとも知っているかどうかがかなり大きなポイントなので、そこは自分自身に大きなマイナスだ。ただ見終わった映画が面白いと、一気にその歴史について知りたくなるという良い部分もある。
比較的歴史好きの自分がどうしてこれまでアメリカ史を知らなかったか、興味なかったかというと、まずその歴史の浅さがネックとなっていた。実際独立戦争前まではいろんなヨーロッパの国が面白半分に植民地にして、勝手に勢力抗争をやっていたので、その時代も含めてそれ以前も、どうしてもヨーロッパ各国の歴史を追っていきたくなる。また新大陸にバンバン送られてくるニガーの奴隷さん達の事をリアルに想像するとかなりせづなくなるので、正直その部分は避けていたというのもある。象徴的な資料としてよく見る「すし詰め奴隷船」の図は酷すぎ。ああいうのを見てリアルに想像すると、当然うんこおしっこは垂れ流しだし、身動き取れないまま新大陸に着くまで自分の一つ上にいるやつのうんこが頭にびっちりかかったまま船に乗ってるのを描いたりすると、ゆううつな気分になる。
歴史認識の有無による差を一つ挙げると、プリ男が自らを「アムステルダム」と名乗った時、真っ先にオランダのアムステルダムが思いついたが、それに対しブッチャーは「俺はニューヨークだ」と含みを持たせて返答している。なぜプリ男がそれを名乗ったかと言えば、ニューヨークがイギリスの植民地になる前、オランダの植民地で「ニュー・アムステルダム」と呼ばれていたということだ。このへんをサクッと知っていればストーリーの中でもっと楽しめたのに。
文化・慣習について、アイルランド移民を中心とした「デッド・ラビッツ」がカトリック教の神父(プリ男の親父)を頭目にしていることは理解できても、神父なのにぶっ殺しまくるのはアリなのか?とか、ピューリタン(プロテスタント)の「ネイティヴズ」がなぜ「ネイティヴ」を名乗ってるのか(ネイティヴ・アメリカン≒インディアンを排斥したことを皮肉っているのだろうか)、それと関連してそれぞれの宗教に対するポジショニング(行事やお祈り)などもきちんとつかめていない。これはもう、キリスト教徒でないとわからん事かもなあ。
自治について、これは現代アメリカでもまだ影響が残っているであろう「連邦主義」的な発想だ。州ごとの自治が大幅に認められ、それぞれの州に特有の制度があるのは今でも度々取り上げられる。それが1800年代中期のニューヨークではどういう感じだったのか。だから、この映画では終盤まで政治統治よりもギャングを背景にした圧倒的な武力による均衡が描かれていたが、プリ男がヘルズゲートに収監されていた10数年間、つまりブッチャーが街の暴れ者の頭目から、地位を得て街全体に影響を及ぼす政治のフィクサーに変化する間のことが見えてこない。
以上書いてきたことのように、この映画は基本復讐劇の体を借りているが実は史実映画で、その本質は「古い時代から新しい時代への転換」だ。徴兵制を免れようと市民が蜂起した時、それを鎮圧したのは軍隊=国家権力だったし、かつて大通りで決着が付くまで闘うことのできたギャング抗争は、軍による艦砲射撃によって始まることなく集結させられた。ここに、ギャング=武力による均衡から国家による統治に変化していったことを象徴している。
金持ちは「貧乏人同士が同士討ちするだろう」みたいなことを言ったが、まさにその通りになったわけだ。プリ男は個人的に復讐を果たしたが、結果的にはブッチャー共々敗北した形になった。ブッチャーを演じたダニエル・デイ・ルイスはこの映画で役者として一人勝ちした奴だ。プリ男やあの女の現代風な風貌が全く違和感のある中、こいつは1800年代中期を貫いた。この映画にして最高の役者だった。
そしてラスト、テーマソングと共にブッチャーとヴァロン神父がニューヨークを見渡す中、時代が進むに連れてどんどん街は発展していく。最後WTCのツインタワーが映った所で暗転。この映画にしてこの暗転はやはりメッセージ性の強い締め方だ。暗転後GANGS OF NEW YORKの題字が。いい感じのラストだ。ヴォーカルも聞こえてきたが、なんか聞いたことある声だ。歌自体もこの映画のために書き下ろされたような詞の内容だ。まーしばらく見てようとだまっていると・・・・・なんとかかんとかU2。あーーーぼのぼのか。この声そうだぼのぼのだ。流石に『この映画のテーマソングをU2』ここはわかるぞ。なんとも粋な計らいだ。
てことで、是非この映画を最初から最後まで鬼畜に見てもらいその感想が聞きたい。野郎は確か歴史があまり好きではないが(違ってたらごめん)、多少なりとも自分にからんでいるのを見るのは面白いのではなかろうか。
長い文章だな。まあ映画の長さを反映してるんだろう。
==============================
上の感想を書いてから他人の感想を見てみると、やたらに評判が悪い。いくつかみてみると、どうも当時の宣伝では「プリ男と女のラブロマンス」が前面に押し出されていたらしい。そりゃーいかんわ。この映画は史実映画として見てこそおもしろさがわかる映画だし、ストーリーやプリ男をメインに見ると非常に中途半端に映るだろう。「ギルバート・グレイプ」ではなく「タイタニック」あたりでプリ男にハマった婦女子などは、プリ男のプリっぷりを堪能するはずが血と暴力の残酷描写にノックダウンだろうな。
これは、プリ男という集客力のあるアイドルをキャスティングせねば興行収入につながらないであろうというスポンサー・販売会社の思惑と、プリ男をキャスティングしさえすれば潤沢な資金で自分の好きな映画が撮れるという個性派監督スコセッシの思惑が変な形で結びついた結果だ。ハリウッド大作の悲しさだ。そして、スポンサー・販売会社の思惑に飛びついた観客は正直この2時間半以上の映画を良く我慢したと思う。南無。
リバプール
< UCL2004-2005 FINAL @ Ataturk Olympic stadium 2005.05.25 >
決勝に限って見てみると、優勝したからMOMがジェラードになったが、前半のままACミランが優勝していた場合は間違いなくカカになっていただろう。全得点に絡んだというだけでなく、カカはモダンなトップ下の理想と言えるような動きを常々していて、まあこれはピルロという中盤の底にパサーがいるから成立してるのかもしれんが、トップ下としてのFWへのラストパス出しだけでなく、自ら局面を切り開いてフィニッシュまで結びつけるテクニックもある。一番の特徴はそのシュート精度だ。
試合の流れはもう見たまんま。前半ミラン、後半ミラン、延長ミラン、PKドゥデク。こういう認識で良いと思う。ただ、「後半ミラン」に関しては間の7分だけわけわかんない時間があったということだ。延長に入ってからは、PKで勝つというリバプールのチームとしての意志統一がされたような戦いだった。実際トップのシセと両サイドのルイス・ガルシア、スミチェルがカウンター要因として残っているだけであとはユベントス戦の2nd-leg、チェルシー戦の1st-legで見せたような守備で頑張るチームになっていて、ベニテスの事だからPKまで行けばなんとかなる自信はあったのだろう。
圧倒的に押された側がPKまで凌ぎきると、PKで優位に立てるというのはよくある展開なんだが(先週のFAカップファイナルもまさにその形だった)、実際PKではミランの1・2人目のセルジーニョ、ピルロが立て続けに外してしまった。このレベルになるとPKは技術よりも最早メンタルの要素が強くなるのだろう、その精神的な圧迫感がもろに出た形だ。53分から60分の間での3失点はアンチェロッティも後日談で「なにがなんだかわけわからんかった」と語っていたようにミランも相当まいったことだろう。そして追いついた後はリバプールサポーターも復活し疑似アンフィールドの雰囲気を作り出したし、PKではリバプール有利の要素が大きかったということだ。
<ウリエ→ベニテス 変化と効果>
以前書いた文章では「ジェラードとシャビ・アロンソの、センスの違うロングパスがチームにフィットすれば何かやらかすかもしれん」みたいな事を書いたが、正直アーセナルすら達成していないUCL制覇を成し遂げるとは思ってもいなかった。リーグの優勝が早いうちにチェルシーにほぼ決定となった時点で、UCLにチームの比重をシフトしたと思われる。そのためかUCL直後のプレミアリーグの試合では全く勝てなかった。また現有戦力からして、長いリーグ戦で安定した勝ち点を積み上げるよりも、ホーム&アウェイルール・一発勝負のUCLの方が断然勝ちやすいという思惑もあっただろう。なんせホームは「This is Anfield」、圧倒的なサポーターが文字通りサポートしてくれる。ユベントス・チェルシーに関してはホームの前半30分間主導権を握り勝負を決め、後の60分+アウェイ90分を守りきるという戦術で勝ち上がったほどだ。その守備では要であるヒーピアを中心に、魂で守りこのUCLでDFとしてかなりの経験を積んだキャラガー、両サイドのフィナンとトラオレは激しい上下動で攻守に貢献した。ドゥデクはレバークーゼン戦のホームでのプレゼントゴールなど、ちょいちょいミスはするものの、決勝でも何度と無くみせたように基本的には凄いキーパーである。
ここで今期リバプールの基本フォーメーションを見てみると、パターンは色々あるが最も結果が出ているのは決勝の後半でも採ったジェラードをCH兼トップ下気味に配置した4-2-3-1の形だ。1トップはスピードでガチャガチャ動くタイプのバロシュかシセで、左リーセ・右ルイスガルシアの両サイド固定、そして肝心なのが中盤の位置に長短のパスでリズムや展開を生み出すシャビ・アロンソと、もう一人はハマン・ビスチャンあたりの守備的な役割を置いたことだ。この役割もバルセロナのシャビ・マルケスの関係ほどはっきりしておらず、基本的にジェラードも含めたCH3人は守備もするしロングレンジのパスで展開も作る。またCHが3枚いることで、やや前目のジェラードが大胆に攻撃参加できるというのが一番良いところだ。
攻撃に関して変化をもたらしたのがルイス・ガルシアだ。もともとテクニックが非常に巧みで、ポジショニングがいいのでパスの出し手としても、またFWの裏・FWが作ったスペースに飛び込んでパスの受け手としても一番活躍した。
<シーズンコンディション>
プレミアリーグも含めて、今期のリバプールはベストメンバーを組めた試合の方がかなり少なかったのではなかろうか。覚えているだけでもシセ・バロシュは骨系の怪我で長期離脱しリーグ戦用FWとして急遽モリエンテスを獲得したほどだ。チームの中心であるCHのジェラード・シャビアロンソ・ハマンも変わり交代に怪我で離脱しており、この決勝で漢を上げたであろうGKドゥデク・2ndGKのカークランドもたびたび怪我で、ユベントス戦では3rdGKのカーソンが入った。他にもシナマポンゴル、キューウェル、メラー、などなど、端的に言えば名前も聞いたこと無いようなウェルシュ・ポッターという選手がしばらく控えに入るほどの有様だった。
<総括>
正直この優勝は圧倒的な力でねじ伏せて勝ち取ったものではない。仮にACミランが優勝していればその通りだったが、怪我人が多く不利な状況の中、ベニテスの巧みな戦術・采配とジェラードを中心とした気合と根性の組織サッカー、そして「You’ll Never Walk Alone」の野太い声がチームを後押しして勝ち取った一種の伝説的な勝利だ。GL第6節のオリンピアコス戦の逆転劇も後半に3点決めた。交代直後のシナマ、当時リーグも含めてラッキーボーイだったメラー、いかにもジェラードらしい強烈なミドルシュート。そして今回の「7分で3点」は伝説を象徴するにふさわしい。同じイングランドのマンチェスター・ユナイテッドがトレブルを達成したときのUCLバイエルン戦のロスタイム大逆転を想起した人も多いだろう。シャビ・アロンソの加入を機に個人的には注目し始めたリバプールだが、シーズンを追っていって非常に面白かった。優勝おめでとう&ありがとう。