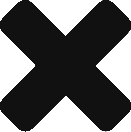裕福な女性を詐欺して大金を得ている詐欺師と、その男に弟子入りしたペテン師の対決話。
「端的にいえば詐欺師は役者であり信頼関係など心理的な刷り込みを行うのに対し、ペテン師は口先やもっともらしい理屈を使い、損得の価値観を操って被害者に利益があるように錯誤させ、金品を騙し取る者。」 – Wikipediaより
という違いらしい。
中盤あたり、女が実は歯磨き粉会社のオーナー子女でなくミス歯磨きで、5万ドル払うと文無しになるというのが暴露されたあたりから、本筋とは別の可能性も感じられ実際その通りだったのだが、見る側の予想と実際の結果が同じだからと言って、面白さが損なわれたわけではないのが本作の出来を良く表している。ストーリーは一本道でわかりやすく、時代的にも演出は洗練されていないが、この観後感はなかなか感じることはできない。
この仕掛けというのがよく出来ていて、詐欺合戦という設定上様々な秘密や嘘が手段として用いられるのだが、これらは見る側に全て公開される。一方、メイン登場人物三人のうち男二人はそれぞれ片側(自分)の秘密や嘘についてしか知らず、女については(形式上)何も知らされていない。つまり本作の場合、序盤で情報は見る側のみに全てオープンにされるので、目的に対して使われる嘘や方便・秘密がそれぞれ一々意味を持ち、やがて目的へと収束していくので能動的にならないわけがないのである。
だから男二人が結局女にしてやられた後も、「なんでそんな簡単にひっかかるんだよ」だとか「詐欺しようとして逆にハメられて馬鹿じゃねーの」とかいう感想は一切無く、まるでスポーツの好ゲームを見た後のような、お互いの健闘を称えたいような気持ちになった。ペテン師の動と詐欺師の静が明確に使い分けられ好対照なのもわかりやすい。ハメられた後二人が「いやーすげえ女だなあ」となった後ですんなり別れるというラストでも、その潔さが落語のサゲのようで十分満足いくほどである。
ところがこれでストーリーは終わらなかった。見る側の(少なくとも俺の)予想を上回るラストにさらに満足度は高まった。潔さから一転ルパンの不二子オチのような爽快感に大満足の終幕だった。