結婚式で親族を惨殺された嫁が復讐の旅に出る話。
クエンティン・タランティーノ監督作品第4弾。これまでの3作で共通したのは、映画の方法としての時間ずらしと、カスがカスなりの見栄・論理で行動しているということ。そして本作は映画監督として大御所の部類に入った感のある、つまり金はあとからついてくるものとしてまず自分が作りたいものがありきである状況のタランティーノが作った映画だということだ。
それは如実に感じられる。まず日本を舞台にして「日本のやくざ映画」を作ることができる状況に持っていったこと。タランティーノが映画マニアであり、仁義なき戦いなど日本映画が大好きなのは有名だ。そしてその波及効果として日本人の俳優が多く登場し、英語が話せる感じのおもしろ日本人として千葉真一御大、深作つながりとしてGOGO、またハリウッドのアジア系俳優でコストパフォーマンス今んとこナンバーワンのルーシーリューが準主役をやっている。反面やつが出るとその映画全体が安っぽくなってしまうという悪い面も同じ。
ガンを常備しているギャングではなく日本のやくざということで、刀を使った時代劇のような映像をやりたかったのかもしれんが(クライマックスの対決では修羅雪姫のテーマ曲が流れる)、おもしろ装束のユマ・サーマンとCPルーシーリューでは殺陣の迫力は当然ないし、変な日本語が爆笑を誘うし、正直あの長い大立ち回りの意図がわかんなかった。つまりそれこそが「監督的に無理矢理でもやりたいシーンです。」の表れでもあるんだが。ただワイヤー丸わかりってのはどうなんだろう。チェックしないわけないし、ハリウッド映画のワイヤー多用に対する皮肉めいたわざとの丸出しか。あと梶芽衣子の曲が重要なシーン(クライマックスとエンディング)で用いられているのも、単にタランティーノが好きだからなんだろうなあ。「恨み節」「修羅の花」はそれぞれ梶芽衣子主演の女囚さそりシリーズと修羅雪姫シリーズで用いられた曲で、それら映画はすごくおもしろい。で曲も確かにしっくりくるんだけど、その文化を知っている日本人が見るとどうもおもしろに感じてしまう。
そう、なんつーか全体に流れるテイストは「真面目なおもしろ」ってことになる。タランティーノは日本のやくざ映画が大好きでそれをハリウッドでやろうとした場合に「カタコトの日本語を真面目に話すハリウッドスター」という形が生まれる。そしてそいつらを使い真剣な場面を作ろうとしても、日本人にとってはおもしろな感じになるんだよなあ。
途中からはなんだかSABUの映画を見ているような感覚になった。どこがどうとか正確には言えないが、それだけタランティーノが作った映画、特にレザボアとパルプは世界中に影響を及ぼしたということでもある。よってそのエッセンスを感じ取った監督の作品のような出来に皮肉にもなってしまったのは、タランティーノが作りたいものを作った結果であるという点、つまり今ある引き出しで済ませてしまったということだ。
結果的に今までの予想を超えるような範疇ではなかった。印象深かったのは「今は親指を動かす方が大事」みたいなくだりの部分だけ。そもそもこんな映画(結構ホメ言葉になるなこの場合は)で粗探しをやったり御都合を指摘するのは馬鹿げているのでやめておき、素直にタランティーノらしい映画を日本人の立場で見ておもしろがるのがよかろう。
てことで、純粋に日本を知らない人はこれをどう思うか知りたいところではある。
カテゴリー: 映画
金環蝕 ★★★★★
チョビヒゲガッハッハな政治家と金融屋とマスコミの話。
故小渕元総理大臣のころから段々と薄まってきているようだが、それだけに逆にガハハ系の政治家がよく区別がつくようになってきている。たとえば竹下政権の頃、ガキだったので細かくは覚えておらんが閣僚という閣僚はガハハだったと思う。鈴木ムネオなんてあんなもん甘い甘い。表にしゃしゃり出てくるだけガハハ気質が足りない。ガハハはやはり、表面的には誠実を繕ってはいるものの、料亭に行ったら両サイドに姉ちゃんを座らせて両手で乳を揉みしだいているべきだし、それができるのがガハハの証だ。
そしてまたそういうガハハを相手にする企業家も平気で顔を使い分けられないと身が持たない。西村晃がダム特殊法人の社長を料亭に呼んで、裏取引をねじ込むシーンの変な踊りと髪の乱れっぷり、あれがこの映画の象徴的なシーンだ。
昔はこういうことが公然と行われ、それが記録に残らず当人たちの記憶に眠ったまま、死とともに永久に葬られてしまう。そして今はそういう時代と、それができなくなった時代との中間点にあるだけに、今後どうなるかはわからんが、まあ時代の産物とはいえ日本らしい大作映画だった。
ただ最後、映画の主題の関係上どうしたってガハハ側を勝利させなければならない制作者側の意志があったのはよくわかるが、新聞社社長が闇に葬られるシーンはかなり無理がある。あそこだけ釈然としねえんだよなあ。終わりはよかったが。
ロード・トゥ・パーディション ★★★☆☆
マフィアの幹部マイケルが色々あって息子マイクと一緒に旅する話。
はじめタイトルを「ロード・トゥ・パーティション」と思って、それでマフィア映画となるとなんらかの抗争による別離なのかなと見ているうちに、確かにそんな感じにはなっていくのだが途中で「パーディションという街にいくぜ我々は」というのであ!パーティションじゃなくてパーディションかよと、物語とは全然別のところで気になった。
時代設定はアルカポネのマフィア時代で、その時代にあった実際のマフィアのあり方(早い話がゴッドファーザー的血縁・契り重視)が物語全体のキーとなっている。物心ついたくらいの子供が親の仕事について詳しく知りたがるというのは自然なことだが、この息子マイケルは好奇心が強いつーか行動力があるつーか、結局そのせいですべてが悪い方向に動き出す、また物語が進行するというのがうまい導入だなあと思った。
とこのような導入からクライマックスまで、行動の動機付けや因果関係まで淀みなく、またまた現代ハリウッド映画にありがちな「スチーブンスピルバーグの 映画!こう作ればおもしろくなる」本を見たまんまつくったような、かっちり型にはめた作りになっているので隙がなく面白くないわけがない。と同時にこれも何遍もこういう映画で書いた気がするが、これが一生もんの映画として永年記憶に刻まれるかというと、それは絶対にあり得ないわけで、そもそもこういうのはテーマが何であれ興行重視なんだから余韻はともかく長い間記憶に残るというのは結構まずい。だから敢えてなのかどうだか、パーフェクト超人並みに予算かけて完璧に作るのが特徴である。
なので、マフィアやドンパチ映画に必須なポイントともいえる「銃の撃ち方への美意識」「殺しの美学」なんてものはあまり重視されず、物語に重きが置かれる(象徴的なのは、なんか変な殺し屋がチョイチョイでてくるのが効果的だったり)のが残念といえば残念だ。マイクが売春宿に取り立てに行った時の間合いの取り方、間の作り方はよかったが、あとは殺しに対する怨念のようなものが見えなかった。やっぱマフィアは殺し合いでなんぼ、いや数出せってわけじゃなくて、質がよければ上記のようにワンポイントでも記憶に残るんだよなー。
TAMA CINEMA FORUM
ここのところ、平日は仕事に追われ、休日はbitchとだらだら過ごすと言うパターンが定着している。先々週はアマラオを見に、先週はバカ映画を見に、と言った感じ。
TAMA CINEMA FORUMという映画祭が毎年秋に多摩市で開かれる。このサイトを見ている人は当然知っていることと思うが、俺は全然知らなかった。で、会社の後輩がなぜかこの映画祭の実行委員をやっており、お友達価格でチケットを売ってくれるというので、せっかくだからbitchを誘って見に行くことにした。
後輩が推薦してくれたプログラムがこれ。なんというか、B級映画もいいところだが、これが3本立てで1,000円ちょっとで見られるというのもめったにないことなので、期待半分、冷やかし半分で見に行った。以下はその感想。ちなみに俺はbitchのように映画を(ビデオででも)普段見ることはほとんどないので、気の利いたことは書けないことを了解して欲しい。
・地獄甲子園
漫☆画太郎原作の漫画の実写映画化。評価が高くなかったのは知っていたので、期待せずに見る。案の定、ギャグらしきものは滑りまくっていたが、話の内容には意外と引き込まれる(多分、俺が単純なだけかも)。終わった後の感想。「これって結構いい話じゃない?」と言うわけで、俺の中での「地獄甲子園」は感動巨編ということに決定。
ちなみに、おれたちの後ろで見ていた学生もしくはフリーターとおぼしき二人組は、劇内のギャグを絶賛し、会場内に笑いがあまり起きなかったことをしきりに不思議がっていた。彼らは幸せ者だ。しかし、フォローとして、俺も蛭子さんがスクリーン上でどアップになったときは吹き出しかけたことを付け加えておく。
・ドカベン
77年製作、水島漫画の驚異の実写版。「コミックス第1巻からなぞっているから柔道ばっかりやっていてほとんど野球シーンは出ない」という話はあまりにも有名。しかし俺はドカベン世代でもないし(この映画が制作された年の生まれ)、コミックスは2巻しか読んでないので、俺の中ではドカベンは柔道漫画。
さてこの映画、山田太郎が朴訥とし過ぎ、岩鬼が葉っぱを加えたまましゃべるため、わざわざアフレコしている、マッハ文朱がアレ、等々見どころ満載だが、全体を見ると、基本線としては青春スポーツコメディ。山田太郎が「気は優しくて力持ち」の権化のような存在で、ものすごく分かりやすいいい話になっている。そう、終了10分前までは。
最終場面で、いろいろあって山田太郎は野球部に入ることになるのだが、ここで新任の野球部監督として出てくるのが御大、水島新司(本人)。これが、どこからどう見てもその辺の居酒屋から抜け出してきた酔っ払いとしか言い様のない風体で、そいつが山田太郎を始めとする登場人物にひたすらノックして終わり、という強引な終え方。うーん、どう見ても続編を作りたかったような終え方なんだが、多分なかったんだろうな。
あと、この映画のもう一つの特徴としては、タイアップが死ぬほど露骨だということ。とにかく登場人物がコカコーラを飲みまくり。スポーツ選手でもがぶ飲み。決闘シーンも特大のコカコーラの看板の前。古きよき時代に思わず思いをはせてしまいましたとさ。
・野球狂の詩
ここまで3時間あまり観て、野球シーンが合計15分くらい。素晴らしき「野球狂伝説」だ、と思っていたが、最後の野球狂の詩ではやっとちゃんと野球をやる野球映画となっていた。
この野球狂の詩、自分はコミックスをだいたい読んでいるのだが、個人的には水原勇気が出てくる前の、わき役キャラクター一人ひとりに焦点を当てた一話完結形式の時の方が好きだった。というわけで、水原勇気編はあまり好きではないのだが、水原役の木之内みどりが結構好みだったので、彼女の入浴シーンがあっただけでOK。あと、岩田鉄五郎が投げるときに発する「にょほほーん」と言う声を実際に俳優がやると、とっても間抜けだということがわかった。
さて、この映画の最大の山場(個人的に)である、水原と野村克也(本人)との対決シーン。このときに、やっぱり出てくるんですよ、御大が。
オープニングのスタッフロールの中に、「メッツファン」(主人公のチーム名は東京メッツ)と言う役で入っていたので、どんな場面で出てくるのか楽しみにしていたのだが、登場の仕方がまたすごい。「ファン」と言う役どころのはずなのに、なぜか水原や岩田に会いに普通にベンチまで来る。二人も二人で、「水島先生」と先生付けで呼ぶ。しかもなんのフォローもなしで。この辺、後年「ドカベン・プロ野球編」などで見られるマスターベーション的臭いをすでに感じ取れてしまう。
というわけで、水島作品の一番の見どころは「水島新司がいつどのように出てくるか」ということに尽きることがわかった。っていうかストーリーはベタなので忘れても構わない。後で漫画を読めばいいし。
ちなみにこの映画もドカベン同様、ラストシーンの尻切れトンボっぷりはすごいものがあり(ある意味ドカベン以上)、ここでは書かないが(面倒だから)、「え、そこで終わり?」と思わず言ってしまうこと請け合い(原作もそんな終わり方だったっけ?)。
最後に、野球マニア的な補足をしておくと、この映画が制作された77年(映画での設定は76年ドラフトから77年開幕まで)、オフに「南海ホークス・野村克也選手」役で出ていた、南海ホークス・野村克也選手兼監督は愛人問題がもとで南海を追い出されることになる。ちなみにこのときの愛人が野村沙知代。もう一つ、この映画の重要な設定である、「野球協約上、女性はプロ野球選手になれない」という条項だが、この項目は平成に入ってから削除され、現在は理論上女性のプロ野球選手が誕生することは可能だ。もちろんまだ誕生したことはないが。
以上。最後に10分の短編(漫☆画太郎原作で地獄甲子園の監督が監督の作品)があったがそれは省略。一言で感想を書くと、「三本立て(それもすべてB級映画)は疲れる」。しかし、見終わってしばらくしてから思い返すと、いろいろな発見があってじわじわと楽しくなってくる。来年もこの映画祭に行くかもしれないな。
野球狂の詩 ★★☆☆☆
いきなり水原勇気話。
たぶん企画段階で、水島新司が当時バリバリのアイドルだったであろう木内みどりに会いたいつーか尊敬されたいつーかぶっちゃけ触りたいだけの話がトントン拍子に進み、じゃあ今またファンタジー野球話として好評の野球狂があるでねえがと、そういう感じで進んだのかもしれない。
というわけでドカベンほどおもしろに走っておらず、なんだかんだでまともな映画ちゃあそうなんだがオリジナルが頭おかしいのでやっぱ変な映画だ。
というのも、話の核であった水原と西山さん(一軍と二軍を往来するキャッチャーの人の仮名、絶対に西山さんではない)との絡みが、ここから来てクライマックスになるのではないかという所で尻切れ気味に映画自体が終了してしまうというあっけなさ、そりゃまあ純粋に映画が好きだ!好きだ!な人からは日本映画見放されるのもうなずけるような作品であるし、当時の勢いでごまかせばなんとかなるブームを反映しているような、なんとも中途半端な映画でした。
ドカベン ★★☆☆☆
水島新司 脳内野球漫画のひとつ、ファンタジーな野球の話。
冒頭いきなりドカベン~26巻が好評発売中だよ的なCM映像から入るのがこの時代、この映画のポジションを物語っているという、現代ではありえないつかみの映像でその世界観に巻き込むことにまずは成功してるのではなかろうか。
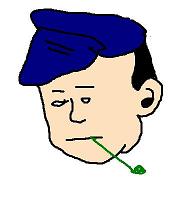
イワキ役は図体のでかい人が演じていて、口にはこれもむかしのバンカラ漫画などでよくある草(こういうやつ→
を常にくわえている状態で話したり、おもしろな感じのことをやったりするのがひどく大変そうだった。さらにイワキが惚れている女に当時女子プロレスで名をはせていたマッハ文朱を起用、学園っぽい話meetsマッハ文朱という組み合わせは古来よりかなりはまる。
で話は野球がほとんど登場しない、クライマックスは柔道の腕一本フェアプレー山田だぜの所で、野球らしいシーンと言えばその後にいきなり登場する作者水島によるノックのシーンぐらいで、当時山田の野球での活躍を期待したであろうチャンピオン読者は失望したことだろう。
それ以上に一番気になったのがコカコーラのタイアップの尋常でない丸出しっぷりであり、マッハ文朱はイワキの応援シーンでコーラを常に携帯、うまそうに飲んだり、でかい宣伝看板が映し出されたりしたのが非常によかった。
という夢いっぱいな映画でした。
地獄甲子園 ★★☆☆☆
漫☆画太郎作全3巻 まだ絶版じゃないので是非ゲットしておこう。
原作における見所の一つである、うんこ・おしっこ・ゲロ・下痢・etc この辺がもろに「アウト」であるのは映画という表現媒体の限界の一つかもしれないが(つーかこんなもんは当然限界であっていいし)、やっぱ画太郎漫画の他メディア化というのはかなり難しいものだというのを再認識するような仕上がりになっていた。
たとえば上記の見所は自主規制であったり倫理規制であったりするが、それ以外の「意図的なコマコピー乱発」「背景は手抜きでもばばあやじじいはかなり綿密にしつこくリアル」といった要素すら映画では安っぽく、到底見るに耐えないものだというのが大きく印象として残った。
そんで内容以上に、自分が見ている後ろに座っている人達が大絶賛していたというのが、そっちの方が作品の出来よりむしろ気になった次第。
キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン ★★★★☆
気の利いた少年が小切手を偽造したり、職業を偽って働いたりする昔ならではの話。
フィクションにおける悪党話というのはおもしろい。勝手に面白くなる。例えばそういうものの代表作と言っていいルパン三世は一般的に面白い作品として認知されているし、モンキーパンチがアクションで連載していたきったない作画の漫画の範疇を飛び出して、今や山田康雄や栗田寛一らが声優をやっているアニメの方がイメージ強いぐらいだ。そのルパンで展開されるのは基本的に金品を盗難するという泥棒行為であり、現実にああいう集団がいると、おもしろおかしい温かい目で見られるのではなくて、早く死んで欲しい人達という熱い血潮が燃えている感じになる。
本作もそういう部類の「詐欺師」が主人公で、しかもこれは現実にあった話であるからなおいっそうタチが悪い。ギャンブルやりまくってサラ金に借金を作りまくり、挙げ句の果て突発的に銀行強盗をやっちゃろうみたいな軽いノリではなく、犯罪を遂行しようと本気になって取り組めば、この時代ならよっぽど馬鹿でない限り恐らくそれは高い確率で成功するということだ。それはまず、犯罪の当事者になるということは通常考えられる範囲ではないイレギュラーな事態だという点が大きい。コンビニでボーっとしてたら目の前に包丁突きつけられていたというような「犯罪丸出し」のシチュエーションではなく、この映画におけるような、まず考えもしないイレギュラーなものならば多くの人間が詐欺につかまされる。
ただこれは現代では恐らく成立しないだろう。小切手の偽造にしろ職業なりすましにしろ、前者はスキャニングとかでバレバレになるし後者はID管理でモロバレ、この点フランクは生まれてきた時代が当てはまってうまくいった感じだ。
で最後は予想通りその後のフランクについて述べられていたんだが、まあ成功したのはいいとして、彼が使い込んだ数百万ドルの金の賠償はどうなったかが気になった。かなり気になった。
ボウリング・フォー・コロンバイン ★★★★☆
アメリカ・コロンバイン校で起こった、生徒による銃乱射事件を題材にしたドキュメント映画。
話の持って行き方がかなり強引なのと、これは一応アメリカ銃社会のおかしなところを探っていくというドキュメンタリーであることから、インタビューや映像の切り口も必然的にそういう寄り方になってしまうという前提の元に、これがアメリカの全てではなく話半分で見る必要があると思う。一つ論調を定めないとエンタテイメントとしてまとまらないというのはしょうがない部分だ。
ただそういう客観的な視点に立つというのをベースとしても、最も客観的である統計を見て確かにおかしいなと感じてしまう。まずアメリカと日本を比べると人口が約3億:約1億3千に対して年間の銃による被害者が約11,000:約40。これは単純に、社会における銃の普及率と直接的に関係していると思う。要するに、あいつぶっ殺したいと思っても日本では手元に銃がないからあまり手軽ではなく、別の手段を用いたり断念したりすると言うことだ。
ただし、その後語られるように銃の普及率がアメリカとカナダではほとんど変わらないのに、人口が約3億:約3千万に対して年間の銃による被害者が約11,000:約200。人口比が10分の一だとしても驚異的に少ないことから、アメリカで銃犯罪が多いのは銃がたくさんあることが一番大きな理由であろうが、それだけではない何か背景があると考えられる。
簡単に銃が購入できるという異常さ、マリリンマンソン、NRA、アメリカの歴史、偏向的なメディアなどマイケルムーアは色々な理由を出しているが、これ自体は先進国なら少なからずあるような、社会が煮詰まった状態での汚物を論ってるだけで、それがアメリカだとどうしても銃と絡んでしまうという話だ。結局そこはワイドショーとあまり変わらない、ジャーナリスティックな視点で問題点を列挙しているだけで、根本的な解決にはならない。最後の方にムーア自身が行動する部分もあるが、なんかいいわけがましい感じがする。
とはいえ社会問題に対して考えを想起させるようなインパクトのあるドキュメンタリーを作ったというのと、ポーズとはいえそういう問題に対して自ら行動し、結果的にKマートの弾丸規制に大いに貢献した姿勢はすごいと思うし、説得力はある。一度銃というものが認められた以上今後も無くならないとは思うが、それに対し問題提起していくのはいいと思う。
アナザーワールド 鏡の国のアリス ★☆☆☆☆
いきなり鏡の向こう側に行ってしまう話。
根性がねじ曲がっているので、思春期に完全否定したものは今後恐らく一周することはないであろうと、今のところ感じている。「ダンス」しかり「ミュージカル」しかり、その中の一つが「ファンタジー」という大きくて曖昧な項目だ。この映画はその完全否定のど真ん中をぶち抜いてくれているわけで、つまりそういうことだ。
それを再確認させてくれたことは間違いないんだが、これが仮にアニメーションならまだいけるかなと思うので、完全否定にも多少のブレはあるようだ。大体がファンタジー・メルヘンといった項目は、なるべくなら現実離れしたほうがいいし、場合によってはそれがシュールな笑いの方向に向かうこともあるが元々そういう方向性を指向していないので、多くの場合は「奇抜な格好をした人が、それらしいフワフワした会話を展開する」という構成になる。要は現実と境界をばっさり引いて(今回の場合はそれが鏡だった)、いかにその世界観に引きずり込めたかが全体的な印象の違いになる。あーその時点でだめなんだなあ俺は。
例えばこの映画ではもちろん奇抜な格好をした人がたくさん出てくるが、そのたびに「あーなんでこいつこんな変な格好してんだろ」「よくそれで今日の晩スーパーで買い物できるな」「今日の昼と夜のギャップを映画にした方が絶対おもろいぞ」「はいカットて言われた直後の顔見てー」とか、ああこれファンタジーに手を付けてはいけない人種の人だろう。
ファンタジーという定義も凄く曖昧なんだが、そりゃ「NHK正午のニュースはとてもファンタジーだ」という輩はあんまいないが、「NHK教育はある意味ファンタジー」「ガンダムは立派なファンタジーだ」「渡る世間は鬼ばかりについて今までファンタジーの中のファンタジーだと思っていた」という人はいるだろうし、それは個人個人の感覚による。まあ奇抜な人がいっぱい出てくるのは、個人的にまったく受け付けられるものではないというのは間違いない。
にしても原色のコントラストを多用した画面構成は見事だし、「あーこういうの好きな人が見るといい感じなんだろうなー」というキャラ付けもされているようだ。あとアリス役の人がかわいい。
すまん。レンタル屋で目的なしの無作為抽出で手に取ったのがこれだったんだ。この映画に悪気はねえんだ。悪気があるのはこっちの方だ。